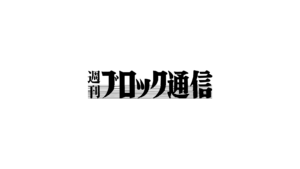脱炭素を使える制度に~理念と現場をつなぐ三つの条件
国土交通省は4月に発表した「脱炭素アクションプラン」で、2027年度からの「低炭素型コンクリート等の原則使用」を打ち出したが、コンクリート製品業界の反応は様々だ。一方で、調達や設計の現場では、すでに制度運用に関する混乱も起き始めている。そもそも高炉スラグ微粉末やフライアッシュなどのセメント置換材料は、地域によって調達の可否が大きく異なる。国交省本省はそうした地域格差を踏まえ、無理な適用を求めるつもりはないとしているが、その意図が地方整備局や自治体の発注担当にまで十分に浸透しているとは言いがたく、現場に戸惑いと不信を生んでいる。
もう一つ、より根深い課題がある。それは、低炭素型材料が「高コスト」であるという事実だ。これは避けがたい側面であり、企業が技術開発に乗り出す際にも織り込み済みの前提だった。だが、発注機関には「公共工事を税金で実施する以上、コストは看過できない」という暗黙の論理は根強い。会計検査が念頭にあると推察するが、カーボンニュートラル2050の実現に向けて、脱炭素新技術の採用に二の足を踏むことがあってはなるまい。
技術を開発し、補助金を得て設備投資までしたにもかかわらず、「高いから使わない」と言われてしまえば、企業としてはまさに「はしごを外された」だ。脱炭素型材料はCO2削減に効果があることが分かっていても、「高いから使えない」という危機に直面している。使われなければ、開発した新技術が売上に結びつかず、開発投資も回収できない。ここに、技術開発と社会実装の間の深い溝が横たわっている。
政府が本気で脱炭素を進めたいと考えるならば、制度側に「売れる構造」を組み込む必要がある。たとえば、CO2削減効果を定量化し、総合評価入札の加点対象とする仕組み。設計仕様書の中に、標準材料の適用範囲を環境性能に応じて明示する。あるいは、「材料が地域的に調達困難な場合は、代替方法も可」といった注釈を設計書に添えるだけでも、現場の判断の幅は広がる。
あわせて受発注両者が、脱炭素材料に「もうひとつの価値」を持たせて評価する発想も必要だ。高耐久・長寿命化、省人化や工期短縮との親和性、意匠性や地域資源との組み合わせなど、採用理由を環境性能だけに求めるのではなく、複数のメリットが見込める「使いたくなる材料」であれば、現場の採用判断も大きく変わってくるだろう。
一方、全国コンクリート製品協会は今年の総会で「PCa政治連盟」構想を打ち出した。これまで行政ルートでの意見交換は続けてきたが、発注制度や予算配分など、より政治的な意思決定の場に業界の声を届けることを狙った新たな挑戦だ。ロビー経験の少ない業界にとっては、大きな賭けでもある。だが、社会環境が高度化・複雑化していることを考えると、こうした正面突破が求められる時代に入っていると言える。
また、業界人の中には、テレビやネットメディアで影響力を持つ言論人を味方に付け、世論ルートから政策へ影響を与える方法を模索する声もある。「政治家を動かすより、政治家が無視できない空気をつくる」という考え方だ。制度内と制度外、両面からのアプローチが今、業界に求められている。
脱炭素は理念であり、社会的な方向性である。しかし、理念を現場に押しつけるだけでは制度は定着しない。技術を社会に根づかせるには、売れる構造、使える制度、そして使いたくなる価値──この三つがそろって初めて、真の社会実装が動き出す。