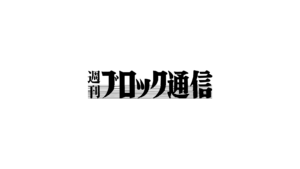12年前、吉野家の牛丼並盛は280円だった
週刊ブロック通信論説委員
株式会社武井工業所 代表取締役 武井 厚
1990年代に日本経済はデフレスパイラルに突入したから、いま50歳代半ばより下の年齢の社会人は、筆者を含め、そのほとんどは長くデフレ環境で働いてきた。多くの中小企業では、ベースアップなど夢のまた夢という時代だった。しかし、2021年後半に日本経済はついにインフレに転じた。12年前の2013年、280円だった吉野家の牛丼並盛は現在498円となっている。
インフレには、良いインフレと悪いインフレがあるとされる。前者は需要の増加によってもたらされ、後者はコスト上昇によってもたらされる。前者は、価格が高くても買う人が増えるから、原価が以前と同じまま売値を上げても売れる。よって企業の利益は増える。後者の場合、高くても買うという人が増えたわけではないので、売値はそのままとなる。原価だけが上昇するため、そのぶん企業の利益は減る。
2022年2月にロシアによるウクライナ侵攻が始まり、エネルギーや食料価格が上昇した。さらに、日米の金利差が拡大して円安が進み、輸入物価が上昇、食料品から光熱費、生活必需品まで幅広い範囲で大きな影響が及んだ。これは悪いインフレと言える。業種や地域性などによって濃淡はあるものの、生産年齢人口の減少を背景に労働者不足も起きている。これは賃金の上昇をもたらすため、あらゆる財やサービスの価格が引き上げられやすい。
吉野家にあてはめると、店舗の光熱費が上昇、為替の影響もあり輸入牛肉価格も上昇、営業時間を維持するためには賃金アップもするしかない。そうなればメニュー価格を上げて利益を確保する必要があるが、市場にはすき家や松屋などライバル達がいて競争がある。牛丼チェーンなどのファストフード業界には「ワンコイン(=500円)」という消費者の心理的な壁もありそうである。ちなみに、牛丼並盛+生卵+おしんこ&みそ汁のセットでオーダーすると811円、同じ組み合わせで牛丼を大盛にすると946円となり、1000円にいよいよ迫る。デフレ世代にとって、吉野家で1000円は異常事態である。
吉野家ホールディングスの業績をみてみよう。2025年2月年計で、吉野家のみの売上高は1265億円で前年比111.1%、利益は80億円で同129.2%と増収増益である。中身をみると客単価は前年比106.9%、客数も同104.2%とそれぞれ増加し、質と量ともに成長している。
コスト上昇分を価格転嫁することで売上の嵩(かさ)は確保できても、現在の社会環境では物的な販売量の増加どころか、維持することすらたやすくはない。産品がルイヴィトンのような桁違いの利益率を持つハイブランドなら別だが、このまま生産量減少トレンドがどんどん進めば、メーカーとしてこれ以上は耐えられないという限界がどこかですぐに来る。今までにはないような質的な後押しがないと、物的な量の確保はできないのではないだろうか。
昔の吉野家には牛丼しかなかったイメージだが、いまは様相が違う。丼ものだけで「からあげ丼」など17種類のラインアップ、定食は16種類、行列ができるカレー有名店が監修したカレーライスに牛丼の具が乗ったメニューまである。こうして、客からより選ばれる状態をつくる。ここから半分想像だが、データ分析により、タイミングよくキャンペーン告知やクーポン発行をして喚起する。メニューが増えることで、サプライチェーン全体のオペレーションがより複雑化するが、DXによりそれをできるだけ抑える。
牛丼だけの一本足打法ではなく、新たな付加価値をいろいろ創り提供するものの質を変え、そのために増加するコストを抑えるための仕組みも作る。吉野家は全くの異業種だが、物的に量を確保するための示唆に富む気がしてならない。